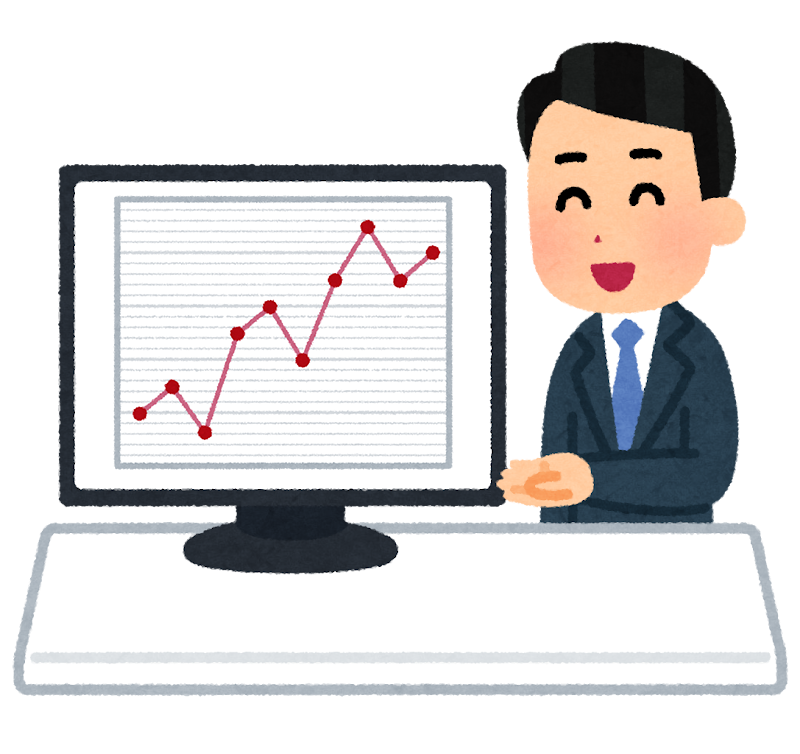ファイナンシャルプランナー(FP)コラム

住宅ローン借入期間の決め方ガイド ~最適な年数と注意点~
執筆者
住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士
お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー 松井 新吾 が執筆しました。

初めて住宅を購入する方へ、住宅ローンの借入期間(返済期間)は何年に設定すべきか悩まれることでしょう。本記事では、住宅ローンの最長期間や年齢制限、ライフプランに合った期間の選び方、期間による毎月・総返済額の違い、フラット35と民間ローンの商品別特徴、繰上返済の活用法、住宅ローン減税との関係、金利タイプとの相性、そしてよくある誤解や注意点まで網羅的に解説します。
1. 住宅ローンの借入期間の上限は?最長年数と年齢制限
住宅ローンの返済期間は最長35年とするケースが一般的です。多くの金融機関で「35年ローン」が主流ですが、住宅の耐久性向上などを背景に、最近では最長50年の超長期ローンを扱う銀行も登場しています。例えば地方銀行の中には50年ローンで月々の負担を軽減できる商品を提供するところもあります。
ただし、借入期間には年齢制限もあります。金融機関は「申込時年齢」と「完済時年齢」の上限を定めており、多くは申込時70歳未満、完済時80歳未満を条件としています。つまり80歳までに完済できる期間が上限となり、35年ローンを組めるのは逆算すると40代前半(目安44歳まで)ということになります。民間ローンでは完済時年齢をもう少し低く(例えば75歳未満など)設定するケースもあり、金融機関によって差がある点に注意が必要です。
ポイント:借入期間の最長年数は商品によって異なりますが、一般的に35年が上限。近年は商品によって40年~50年まで可能な場合もあります。ただし年齢制限(完済時80歳目安)があるため、誰でも50年ローンを組めるわけではありません。ご自身の年齢と各金融機関の条件を確認しましょう。
2. 借入期間の選び方:ライフプラン・年収から考える判断軸
借入期間を何年に設定すべきかは、各家庭のライフプランや収支状況によって異なります。一概に「○年が正解」とは言えませんが、検討する際の主な判断軸は次のとおりです。
- 月々の返済額から逆算する
無理なく支払える月々の返済額をまず決め、それに見合った借入期間を設定しましょう。例えば「毎月の返済は手取り収入の25%以内に抑えたい」といった基準を設け、その範囲で収まる期間を計算します。現在では最長50年まで選択可能ですが、無理のない支払金額になるよう期間を調整することが大切です。 - ライフイベントと収支の見通し
自身と家族の将来計画に沿って返済期間を考えます。定年退職の時期までに完済できるのが理想ですが、子どもの教育費負担が大きくなる時期や、将来の収入変動も考慮しましょう。例えば20代・30代であれば定年まで時間があり35年ローンも組みやすいですが、40代で35年ローンにすると完済時が75歳超となる可能性があり、退職後も返済が続くリスクがあります。その場合は頭金を増やすか借入期間を短めに設定し、できるだけ現役収入のあるうちに完済できる計画が望ましいでしょう。一方、20代・30代は借入期間を長く設定しやすい反面、年収が低めで勤務年数も浅いため希望額を借りられないケースもあります。ご自身の年収の将来見通しや家族構成の変化(出産や転職など)も踏まえて期間を検討しましょう。 - 借入額とのバランス
希望の借入額に対して何年なら無理なく返済できるかシミュレーションします。借入期間が長いほど同じ金額でも毎月返済額を抑えられる反面、期間を短くすると月々負担は増します(後述)。例えば金利1.5%で借入額2,900万円の場合、20年返済では月約14万円、35年返済なら月約9万円の返済になります。家計に余裕を持たせたいなら長めの期間で借入可能額を増やす方法もありますが、長く借りすぎると総支払額が増える点(後述)とのバランスを考える必要があります。 - 将来の収入・支出の不確実性
昨今の社会情勢や景気変動も踏まえ、「思いもよらない出来事が起きても耐えられるよう慎重に期間を決めたい」という視点も重要です。例えば将来的に収入減や失業リスクが不安な場合、月々返済に余裕を持たせるため長めの期間を選ぶことが一つの安全策です。一方で収入増が見込める・繰上返済できる蓄えがある場合は、敢えて短めに設定して早期完済を目指す選択肢もあります。
ポイント:「何年借りるべきか」に正解はないものの、基本は家計に無理のない月返済額から期間を逆算することです。自分たちのライフプラン(収入の将来予測、子育て・教育費、退職時期など)を洗い出し、それに沿って完済目標時期を定めましょう。「◯歳までに完済したい」「月◯万円までなら払える」という基準を持つことで、適切な借入期間が見えてきます。
3. 借入期間でどう変わる?毎月の返済額と総返済額のシミュレーション
借入期間の長さは、毎月の返済額と総返済額(支払利息を含む)に大きな影響を与えます。その関係はシーソーのようなもので、期間を長くすれば月々の返済額は減る一方、支払う利息が増えて総返済額は大きくなります。逆に期間を短くすれば月々の返済額は増えるものの、利息負担が減って総返済額は少なくなります。
具体例で比較してみましょう。借入額2,900万円・金利1.5%・元利均等返済の場合で考えます。
- 20年ローンの場合
月々の返済額は約14万円になります。この場合の総返済額(元金+利息)は約3,359万円です。 - 35年ローンの場合
月々の返済額は約9万円となり、20年ローンに比べて毎月約5万円負担が軽くなります。一方で総返済額は約3,730万円となり、20年返済に比べ約371万円も多く支払う計算です。
より上記の例をまとめると、借入期間を15年延ばす(20年→35年)ことで月々約5万円の負担減になる一方、総支払額は約370万円増加することになります。要するに、「毎月の負担軽減」と「支払総額の増加」がトレードオフの関係にあるわけです。
補足:上記シミュレーションではボーナス払い無し・固定金利で比較しています。変動金利の場合、将来金利が上昇すると長期ローンでは総支払額がさらに増える可能性があります(後述の金利タイプの項参照)。
ポイント:借入期間を長くすると、毎月支払額は少なく抑えられるものの、支払う利息総額が増えトータルコストは高くなります。借入期間を短くすると、毎月の負担は重くなりますが利息を抑えられ総支払額は小さくなります。自分の優先順位(「月々の負担を減らしたい」or「総支払額を減らしたい」)や返済能力に応じて、どちらを重視するか考えましょう。多くの方は家計に無理のない範囲でなるべく短めに返したいところですが、生活に支障が出るほど月返済額を上げるのは本末転倒です。適切な期間設定のために、必ず事前に住宅ローンシミュレーションで返済額と総額の試算をしてみることをおすすめします。
4. フラット35・民間ローンの商品別違いと借入期間の特徴
住宅ローンの商品には、大きく分けて民間銀行等のローンと、住宅金融支援機構のフラット35(全期間固定ローン)などがあります。これらの商品ごとに借入期間や金利の特徴が異なります。
- フラット35(住宅金融支援機構+民間提携ローン)
商品名が示す通り最長35年までの全期間固定金利型住宅ローンです。借入時に完済までの金利と返済額が確定するため、長期のライフプランを立てやすいのがメリットです。完済時年齢の上限は80歳(申込時の年齢から80歳になるまでの期間が最長借入期間)とされており、申込年齢によっては35年より短い期間が上限になる場合があります。フラット35自体は最長35年ですが、借入期間は15年以上(満60歳以上の借入では10年以上)という下限も設定されています※。また、フラット35を拡充した商品として、省エネ性の高い長期優良住宅等を対象に返済期間を最長50年まで延長できる「フラット50(長期優良住宅タイプ)」を提供する金融機関もあります。 - 民間銀行の住宅ローン(変動金利型・固定金利期間選択型など)
民間の金融機関が提供する住宅ローンの多くも最長35年まで設定できるものが一般的です。ただし商品によっては40年まで延長できたり、近年では地方銀行やネット銀行で最長50年の超長期ローンを扱う例もあります。例えば筑波銀行では融資期間を最長2年~50年まで柔軟に設定できる商品を提供しています。民間ローンの場合、完済時年齢はフラット35より低め(例えば75歳未満など)に設定されていることが多く、借入時の年齢が高い場合は自ずと借入期間も短く制限されます。また金利タイプを選べるのも民間ローンの特徴で、返済期間によっては後述の通り金利タイプ選択に制約や違いがあります。例えばりそな銀行では借入期間を36~40年とする場合、金利が0.1%上乗せされるなど、超長期借入時には金利条件が変わるケースもあります。 - 公的ローン・自治体ローン・財形住宅融資
一般的ではありませんが、一部の勤務先の財形貯蓄制度を利用した住宅融資や、自治体が行う融資制度が利用できる場合もあります。これらも概ね返済期間は20~35年程度で、完済時年齢制限があります。商品によって金利や期間は異なりますので、利用を検討する際は各制度の条件を確認してください。
※フラット35の最低返済期間について: フラット35では当初から短期間で完済するローンは想定されておらず、通常15年以上の返済期間(借入時年齢が満60歳以上の場合は10年以上)が条件となっています。つまりフラット35では10年未満など極端に短いローンは利用できませんので注意しましょう。
ポイント:フラット35は最長35年固定金利で金利変動リスクなし・計画重視の方向きですが、期間延長の柔軟性はなく基本的に35年超は利用不可です(長期優良住宅の場合の特例を除く)。民間ローンは変動金利や一定期間固定金利など選択肢が豊富で、商品によって40年~50年まで設定可能なものもあります。その代わり金融機関ごとに完済年齢条件や金利条件が異なるため、「長く借りたいけれどどの銀行でも可能とは限らない」点に注意しましょう。例えばつくばエリアの地方銀行である筑波銀行は最長50年に対応していますが、他の銀行では35年までしか認めない場合もあります。各商品の特徴と制約を把握したうえで、自分に合うローンを選ぶことが重要です。
5. 繰上返済の活用法と長期借入のリスク・メリット
住宅ローンを計画通り返済していく中で、まとまった資金に余裕ができた場合に活用したいのが「繰上返済」です。繰上返済とは、予定より早く一部または全額を返済することで、残りの元金を減らし利息負担を軽減する方法です。借入期間が長期にわたるほど支払利息が大きくなるため、繰上返済によって返済期間を短縮したり毎月返済額を軽減したりすることは、総支払額を抑える上で非常に有効です。
一方で、長期の借入にはメリットとデメリットの両面があります。ここでは長期借入のメリット・リスクと、繰上返済を上手に活用するコツを整理します。
メリット(長期借入の利点)
- 月々の返済負担が軽い
借入期間が長ければ長いほど、同じ借入額でも毎月の返済額は小さく抑えられます。その分、教育費や生活費に余裕を持たせることができ、家計破綻のリスクを下げられます。「ローンに追われる」ストレスを減らし、万一収入減少などが起きても返済困難に陥りにくいメリットがあります。 - 借入可能額を増やせる
月返済額に余裕が生まれる分、金融機関の審査上もより多くの額を借りやすくなります。希望の物件価格に対して自己資金が不足気味の場合でも、期間を伸ばすことで所要資金を調達できる可能性があります(ただし借りすぎには注意)。 - 柔軟に繰上返済しやすい
あらかじめ長めの期間で組んでおけば、後から繰上返済で短縮する自由度があります。逆に初めから期間を短く設定してしまうと月々の支払が重く、途中で延長するのは容易ではありません(延長には金融機関の審査や条件変更が必要で、基本的に簡単ではありません)。「長く借りておいて、余裕ができたら繰上返済で早く返す」という戦略は、多くのFPも推奨する方法です。
デメリット(長期借入のリスク)
- 総支払額が増える
前述の通り、借入期間が長いほど支払利息が増えて総返済額が大きくなります。特に低金利とはいえ30~40年という長期間では利息総額が数百万円単位で膨らむため、「利息のムダ」を多く払うことになります。長期ローンは家計に優しい反面、この利息コストが最大のデメリットです。 - 老後までローンが残るリスク
長期ローンでは完済が老後の年齢に及ぶ可能性があります。定年後に十分な年金や蓄えがないと、リタイア後の返済が家計を圧迫する恐れがあります。退職金で一括返済する計画も、予想外の出費や退職金制度の変化で思うようにいかない場合があります。なるべく現役中に完済できるよう計画するのが安全策ですが、長期ローンだと意識しないとズルズル返済が長引く危険があります。 - 金利変動リスクが長期間続
(※固定金利型であれば当てはまりませんが)変動金利で長期ローンを組んだ場合、将来の金利上昇による返済額増加リスクに長期間さらされます。借入期間中に経済環境が大きく変わり金利が上昇した場合、長期ローンほど総支払額への影響が深刻になります(詳細は後述の金利タイプの項で解説)。 - 心理的負担
長期間にわたり多額の借金を抱えること自体、精神的な重荷になる人もいます。「○十年先までローンがある」と考えるとプレッシャーを感じる場合、たとえ返済可能でも精神面の負担が無視できません。ライフステージの変化(転職・病気・離婚など)のリスクも長期間には内包されるため、計画通りにいかない不安も付きまといます。
繰上返済を活用して賢く利息カット
上述のデメリットを緩和しメリットを活かす方法が繰上返済の活用です。繰上返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類がありますが、特に効果が高いのは期間短縮型です。まとまった資金ができたときにその分を返済に充てることで完済時期を繰り上げ、本来払うはずだった将来利息をカットできます。繰上返済のタイミングについては、後述する住宅ローン減税との兼ね合いも考える必要があります(住宅ローン減税を受けている期間中に繰上返済すると減税額が減ってしまう点に注意)。一般的には「住宅ローン減税の適用期間が終わってから繰上返済するほうが有利」とも言われます。なぜなら減税期間中は年末残高の一定割合が税控除されるため、慌てて元本を減らすメリットが薄い場合があるためです。実際、住宅ローン控除の恩恵を受け終わる借入後13年目以降に繰上返済するのがおすすめとする専門家もいます。減税期間中はその分のキャッシュを手元に残し、期間終了後にまとめて繰上返済して元本を減らすという計画です。
もっとも、繰上返済の判断は金利水準によっても異なります。例えば住宅ローン金利が高め(減税効果以上)であれば、減税期間中であっても早めに繰上返済した方が総支払額を減らせるケースもあります。逆に超低金利下では無理に繰上返済せず手元資金を他の運用や予備費に回す選択も一理あります。いずれにせよ、繰上返済は家計に無理のない範囲で計画的に行うことが大切です。月々の返済を優先しつつ、ボーナスや余剰資金の一部を賢く繰上返済に充てていきましょう。
ポイント:長期ローンの取り方としては、「当初は長めに借りておき、後から無理のないタイミングで繰上返済していく」方法が現実的で安心です。短期で組んで毎月カツカツになるより、長期でゆとりを持たせ必要に応じて早期返済する方が安全策と言えます。ただし繰上返済のしすぎで住宅ローン減税の適用条件(返済期間10年以上)を下回らないよう注意しましょう。繰上返済する際は金融機関の手数料が無料かどうかも確認しつつ、家計全体の資金計画の中でバランスよく活用してください。
6. 住宅ローン減税と借入期間:税制面から見た影響
マイホーム購入者にとって嬉しい制度である住宅ローン減税(住宅ローン控除)ですが、この適用条件にも借入期間が関係しています。結論から言えば、住宅ローン減税を受けるには「返済期間が10年以上」であることが必要条件の一つです。したがって借入期間が10年未満のローンには減税が適用されません。極端に短い返済計画だと税制優遇が受けられない点に注意が必要です。
また、借入期間そのものは減税「控除期間」の長さにも影響します。現在の住宅ローン減税は原則13年間(以前は10年)にわたり、年末のローン残高の0.7%(上限あり)を所得税等から控除できる制度です。借入期間がこの控除期間より短ければ、当然控除も途中で打ち切られます。例えば返済期間が8年のローンでは、10年以上という適用条件を満たさないため初めから減税が受けられません。返済期間を12年に設定すれば減税は受けられますが、完済が13年より手前になるため控除も完済まで(12年分)で終了します。つまり控除期間をフルに使うにはローンを最低でも控除期間分は残しておく必要があります。
ここで注意したいのが、繰上返済と住宅ローン減税の関係です。繰上返済によって返済期間を短縮しすぎると、残りのローン期間が10年未満となった時点で住宅ローン減税の適用要件を満たさなくなり、以後の年は控除を受けられなくなってしまいます。例えば当初20年ローンで減税を受けていた場合でも、途中で大幅な繰上返済をして残期間が9年になった時点で、翌年以降は減税打ち切りとなる恐れがあります。このため減税期間中に繰上返済を行う場合は、残り期間が10年以上ある状態を維持するか、減税が終わってからまとめて行う方が良いと言われます。
一方で、借入期間が長ければ常に有利というわけでもありません。住宅ローン減税の控除額は年末残高に応じて決まりますが、あくまで上限(新築の場合最大借入残高3,000万~5,000万円※の0.7%)があります。また所得税から控除しきれない分は住民税から控除されますがこちらも上限があります。そのため借入額が大きく期間が長いほど減税額も大きくなる傾向はありますが、支払利息総額と減税額を比較すると、特に金利の高いローンでは利息の方が減税額を上回るケースが多いです。減税はあくまで「戻ってくるお金」であってタダでもらえる利益ではない点に注意しましょう。
※控除上限額は住宅の種類により異なります(認定住宅等は借入残高上限5,000万円、それ以外の新築は3,000万円など)。また2024年以降も税制改正により見直しが行われていますので最新情報を確認してください。
まとめると:
- 返済期間10年以上でなければ住宅ローン減税は受けられません。短期完済のローンや親族からの借入等は対象外となります。
- 減税適用期間(現行最大13年)いっぱい恩恵を受けるには、それに近い期間のローンが必要です。繰上返済で完済時期を繰り上げる際は、減税期間が残っているか検討しましょう。
- 減税を意識するあまり「借入期間を長くしすぎても良い」というものでもありません。金利負担とのバランスが大事です。例えば金利が0.5%で減税控除率0.7%なら恩恵が勝るケースもありますが、金利1.5%なら控除0.7%では追いつかず利息負担超過です。減税期間中の繰上返済についても、金利次第では減税を待たずに返した方が有利な場合もあります。
- 住宅ローン減税は期限が来れば終了します。減税が終わると毎年払っていた税金分が戻ってこなくなるため、「減税後」を見据えて繰上返済や返済計画を立て直すと良いでしょう(減税期間終了後に月返済額が一気に負担に感じるケースもあります)。
ポイント:住宅ローン減税を受けるには返済期間10年以上が必須。借入期間を設定する際はこの条件を満たすようにしましょう。減税の恩恵をフルに活かすには、控除期間中は残高をある程度残しつつ、控除期間終了後に繰上返済で一気に完済という方法が効果的とも言われます。ただし金利や自身の税金支払い状況によって最適解は異なります。減税額に過度に頼らず、「減税はおまけ」くらいの意識で、本来の返済計画を優先することをおすすめします。
7. 借入期間と金利タイプ(固定・変動)の関係
借入期間の長短は、適した金利タイプ(固定金利・変動金利)の選択にも関係してきます。住宅ローンには大きく分けて変動金利型と固定金利型(および固定期間選択型)がありますが、ローンの期間が長いか短いかで金利変動リスクへの向き合い方が異なるため、選び方のポイントも変わります。
一般的に、借入期間が長期(30~35年など)になるほど変動金利のリスクが高まります。将来数十年先まで金利動向を正確に読むことは不可能であり、その間に金利上昇局面が訪れる可能性も十分あります。長期ローンで変動金利を選択すると、仮に金利が上昇した場合の返済総額増加リスクや、最悪の場合月々返済額が増えて家計を圧迫するリスクが大きくなります。そのため、借入期間が長い人や借入額が大きい人、毎月の返済に余裕があまりない人は、多少初期金利が高くても全期間固定金利などを選んで金利変動リスクに備える方が安心と言われます。実際、「35年ローンを組むなら将来の金利上昇に備えて固定金利を選ぶべき」というアドバイスは多くの専門家が指摘するところです。
一方、借入期間が比較的短期(例えば10~20年程度)だったり、借入額が小さい場合には、変動金利のメリットを享受しやすい場面もあります。変動金利は現時点の金利水準が非常に低く設定されていることが多く、短期間で元本を減らせる計画であれば金利上昇のリスク期間も限定的です。そのため、家計に十分な余裕があり自己資金も多め、かつ返済期間が短めという人は、低金利の恩恵で元本を早く減らせる変動金利を選択することで総返済額を抑えやすくなります。実際、近年の低金利環境では新規借入の約7割近くが変動金利型を選ぶ状況となっており、特に短期での繰上返済予定がある人や、将来金利上昇時にも繰上返済や貯蓄で対応できる余力のある人は変動型を選ぶ傾向があります。
固定金利期間選択型(例えば固定3年・10年など一定期間固定し、その後変動か再固定を選ぶタイプ)を選ぶ場合も、何年のローンにするかで考え方が変わります。例えば10年固定は「とりあえず最初の10年は安心だが、その後残りの期間の金利は不確定」という商品です。借入期間が長ければ固定期間終了後にまだ長い返済が残るため、再度金利上昇リスクに直面します。逆に借入期間が短ければ、固定期間終了とともに完済に近づいているのでリスクは小さいです。固定期間選択型を利用する際は、自分の借入期間全体の中で固定期間がどれくらいカバーされるかを意識しましょう。
近年では、変動金利と固定金利をミックスする(借入額を一部ずつ違う金利タイプで組み合わせる)方法も増えています。例えば総借入の半分を全期間固定、半分を変動とすることで、全固定より金利を低めに抑えつつ変動のみよりリスクを減らすという手法です。借入額が大きく期間も長い場合、一つの金利タイプに賭けるのではなくミックスローンでリスク分散するのも選択肢と言えます。ミックス比率や商品選びは難しい面もあるため、利用検討時は金融機関やFPに相談するとよいでしょう。
ポイント:借入期間が長期の場合は、金利変動リスクへの備えを重視しましょう。返済期間中に金利が上振れする可能性を考えると、長期借入者ほど固定金利の安心感に価値があります。逆に借入期間が短期で早期完済の見込みが高いなら、当面の低金利メリットを取って変動金利を選ぶ選択肢も有力です。ただし変動を選ぶなら将来の金利上昇時にも対応できる貯蓄・収入余力があることが前提です。「期間が長い=固定、短い=変動が有利」という傾向はありますが、最終的には各家庭の返済余力やリスク許容度で判断しましょう。迷う場合、固定と変動を組み合わせるミックスローンも検討し、無理のない範囲で金利上昇リスクに備えることが大切です。
8. 住宅ローン借入期間に関するよくある誤解・注意点
最後に、住宅ローンの借入期間について初心者が陥りがちな誤解や見落としやすい注意点をまとめます。以下のポイントに気をつけて、借入期間設定で失敗しないようにしましょう。
- 「長く借りれば月々楽だからお得」という誤解
確かに月返済は軽くなりますが、既に述べた通り長く借りるほど総支払額は増えます。支払利息が膨らみすぎると家計トータルでは損をする可能性が高いです。必要以上に長期間に設定しないよう注意しましょう。「借りられる最大35年(あるいは50年)一杯まで借りておこう」という発想は禁物です。将来金利が上がれば負担増リスクもあります。長期借入自体は悪いことではありませんが、そのコストとリスクを十分理解して選択する必要があります。 - 「短く組めば利息が減って絶対得」という思い込み
期間短縮は利息軽減効果がありますが、月々返済が高額になり過ぎると家計破綻のリスクが生じます。無理な計画で途中で返済不能になっては本末転倒です。返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)は一般に25~30%以内が目安と言われます。極端に短いローンでこの比率が高くなり過ぎないよう注意しましょう。FPからも「返済総額では短期契約が有利だが、無理な短期設定はせず長めの期間+無理のない繰上返済がおすすめ」との指摘があります。メリットだけを見るのではなく、家計に与える負担とのバランスで期間を決めましょう。 - 住宅ローン減税に関する勘違い
「住宅ローン減税があるから利息を払っても得」「減税があるから繰上返済しない方がいい」といった声もありますが、減税は永遠に続くわけではなく最大13年で終了しますし、控除額にも限度があります。実際の利息負担額が減税額を上回るケースが多い点を忘れずに。減税目的であえて借入期間を長くしすぎたり、控除期間中だからともったいなくて繰上返済しないというのも考えものです。繰上返済のタイミングはケースバイケースですが、減税終了後に残高を一気に減らす戦略など、自分に有利な方法を選びましょう。 - 年齢制限の見落とし
借入期間だけに目が行き「○年ローンを組みたい」と思っても、年齢によっては希望通りの期間で借りられない場合があります。多くの銀行で完済時80歳未満など年齢条件がありますので、高齢での借入では自ずと期間も短縮されます。また団体信用生命保険(団信)の加入年齢制限もあり、高齢になるほどローンの選択肢が狭まる点に注意しましょう。逆に言えば、若いうちほど長期ローンを組める余地は大きいですが、それが必ずしも有利とは限らない(上述のように利息総額が増える)ので、年齢=上限期間いっぱいではなく計画重視で期間設定してください。 - 退職後も返せるから大丈夫?
「定年後も働くつもりだからローンが残っても構わない」「退職金で残債を一括返済すればよい」と考える方もいます。しかし将来の健康状態や雇用環境、退職金の額は不確実です。また年金収入ではローン返済が困難なケースも多いです。基本的には定年(またはその少し後)までに完済できる期間に収める方が安心です。どうしても老後まで返済が残る場合は、繰上返済や資産運用で老後の残債減らしの計画を早いうちから立てておきましょう。 - ボーナス頼みの返済計画
借入期間の問題ではありませんが、ボーナス併用払いで月々返済を軽く設定しすぎるのも注意点です。ボーナスは景気や業績で減額・カットされるリスクがあります。特に長期ローンでは景気変動を何度も経験し得ます。ボーナス払い分を当てにした計画は、ボーナス不支給時に行き詰まる危険があります。ボーナス返済は保守的に見積もるか、可能なら無しでも返済できる期間設定にしておく方が安全です。 - 金融機関ごとの条件を確認する
借入期間について「どの銀行でも同じ」と思い込まないようにしましょう。例えばある銀行では50年ローン可能でも、別の銀行では35年が上限ということがあります。また借換え時には、新規より残期間が短くなるため減税の扱いなど変わる点も要確認です。各行の条件やメリット・デメリットを比較検討し、自分に最適な選択をするよう心がけましょう。
以上の点を踏まえ、住宅ローンの借入期間を決める際には総合的な視野で判断することが大切です。一つの要素(例えば月々の支払額の安さや税制優遇)だけに囚われず、長期的な家計シミュレーションを行った上でベストな期間を選びましょう。
9. まとめ:住宅ローン借入期間は何年がよい?失敗しない選び方とは
結論から言えば、「住宅ローンの借入期間にこれが正解という年数はありません」。 家族構成、年齢、年収や将来の見通し、住宅価格、ライフスタイルによって適切な期間は変わります。ただ、本記事で述べてきたポイントを踏まえると、失敗しない借入期間の選び方として次の指針が見えてきます。
- 月々無理なく払える額から期間を決める
まず家計に占める住宅ローン返済負担の上限を決め(目安は手取りの20~25%以内など)、その範囲で収まるよう借入期間を設定しましょう。支払計画に余裕があれば早期完済に越したことはありませんが、無理な短期返済は避け、ゆとりある期間設定にするのが基本です。 - 完済目標時期を意識する
何歳までにローンを終えたいか逆算し、定年退職や子どもの独立時期などライフイベントと照らして期間を検討します。多くの方にとって60~65歳で完済できれば理想的です。難しければ繰上返済前提で70歳までに終える計画とし、老後の生活に支障が出ないようにしましょう。 - 長めに借りて計画的に繰上返済
安全策として、当初は少し長めの期間で契約し、余裕が生まれたら繰上返済で実質的な返済期間を短縮する方法が有効です。こうすることで月々の負担と将来の利息のバランスを取りつつ、状況に応じ柔軟に対応できます。「長く借りて早く返す」このスタンスが結果的に利息の無駄も減らしやすく、リスク管理にもなります。 - 借入期間と金利タイプも合わせて検討
期間が長ければ固定金利中心、短ければ変動金利も活用、といったように金利選択もセットで考えましょう。特に30年以上のローンを組むなら全期間固定や長期固定期間のプランを視野に入れ、金利上昇リスクをケアすることが重要です。
住宅ローンの借入期間は何年が正解か?――それは結局のところ「あなたにとって無理なく、将来設計に合致した期間」です。周囲のケースや一般論に流されず、ぜひシミュレーションを重ねてベストな期間設定を見つけてください。
住宅ローンについては、住宅購入診断士の資格を持つ「おうちの買い方相談室つくば店」のファイナンシャルプランナーに是非ご相談下さい。
茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】
人気コラムベスト5
-
 つくば市の10年特例用地って?
皆さんこんにちは!今回は先日茨城県つくば市のお客様がおうちを建てることが決まった「10年特例用地」についてです!つくば市には10年特例用地として住宅用地や分譲地などが存在します。続きを読む
つくば市の10年特例用地って?
皆さんこんにちは!今回は先日茨城県つくば市のお客様がおうちを建てることが決まった「10年特例用地」についてです!つくば市には10年特例用地として住宅用地や分譲地などが存在します。続きを読む
-
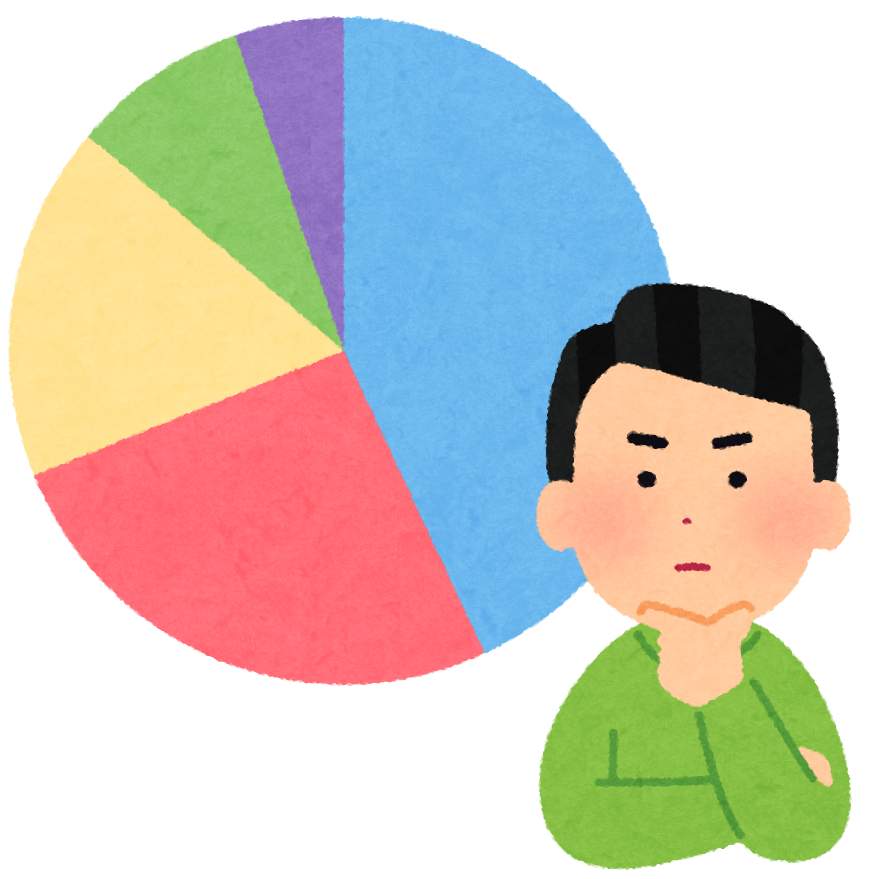 年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫?返済の安全性を考える
初めてマイホーム購入を検討している方にとって、「年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫か?」は大きな不安ですよね。結論から言えば、可能ではあるものの慎重な計画と余裕を持った返済計画が必要です。続きを読む
年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫?返済の安全性を考える
初めてマイホーム購入を検討している方にとって、「年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫か?」は大きな不安ですよね。結論から言えば、可能ではあるものの慎重な計画と余裕を持った返済計画が必要です。続きを読む
-
 住宅ローンの変動金利への誤解と破綻について
住宅購入において殆どの方が住宅ローンでの借入を行いますが、ここで悩ましい問題の一つが「変動金利」と「固定金利」の選択になります。続きを読む
住宅ローンの変動金利への誤解と破綻について
住宅購入において殆どの方が住宅ローンでの借入を行いますが、ここで悩ましい問題の一つが「変動金利」と「固定金利」の選択になります。続きを読む
-
 頭金を運用するという考え方
住宅を購入するときに頭金をいくら入れようかと悩まれている方はとても多いです。また近年、積立NISAやiDeCoなどの資産運用に興味を持たれ、始めてみた方も非常に多いです。続きを読む
頭金を運用するという考え方
住宅を購入するときに頭金をいくら入れようかと悩まれている方はとても多いです。また近年、積立NISAやiDeCoなどの資産運用に興味を持たれ、始めてみた方も非常に多いです。続きを読む
-
 インフレ対策「ローン完済」か「ローン破産」かの分かれ道
日本では、1980年代のバブル崩壊以降、長期間にわたりデフレの状態が続いていました。特に日経平均株価は1989年に3万8,957円をピークに下落し、「3万円台はもう戻らない」との声も多く聞かれていました。続きを読む
インフレ対策「ローン完済」か「ローン破産」かの分かれ道
日本では、1980年代のバブル崩壊以降、長期間にわたりデフレの状態が続いていました。特に日経平均株価は1989年に3万8,957円をピークに下落し、「3万円台はもう戻らない」との声も多く聞かれていました。続きを読む
ご相談者様の声VOICE

-
最初から最後までずっと味方になってくれて、大変感謝しております!
(千葉県船橋市 S様)
-
元々、夫婦で賃貸物件に住んでいてそこまで「マイホーム」の事は近々で考えてはいませんでした。そんな中、住んでいる部屋から一部水漏れが発生!... 続きを読む

-
我が家の現在と将来をきちんと考えて下さったのが「おうちの買い方相談室」でした!
(茨城県つくば市 F様)
-
初めて「おうちの買い方相談室」に相談したのは、土地の購入を考えた時です。現在の収入で住宅ローンを組み、最後まで支払いが出来るのか?住宅ローンの審査が通るのか?不安になり、ご相談いたしました。実は、他のFPさんとも... 続きを読む
住宅購入専門のファイナンシャルプランナー(FP)による
茨城県・千葉県近郊の住宅購入・住宅ローンなどの無料相談予約 受付中です。
 下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
- 住宅購入や住宅ローンについてどこに相談して良いか分からない
- 土地・戸建て・マンションの物件比較・アドバイスもしてほしい
- 住宅ローン返済と資産運用を両立させるにはどうすればいいのか
- 住宅ローンで変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきか
- 住宅価格が高騰していて買えないのでは・・・
- 初めての住宅購入の際、まず何をすればよいのか分からない
- 住宅展示場に行くと営業マンに売り込まれそうで怖い
- お家の建築費以外にかかる費用の詳細が知りたい
- 自分の理想のお家を建ててくれる住宅会社が見つからない
当社は、住宅購入に特化した知識と経験を持つ
独立系ファイナンシャルプランナーとして、
お客様の立場に立った中立・公正なアドバイスを行っております。
| 住宅購入相談の比較 | 当社 | FP事務所 | 他の住宅相談窓口 |
|---|---|---|---|
| 所属 | 独立 | 独立 | 保険代理店など |
| 中立性 | 高い | 高い | 低い |
| 提案内容 | 幅広い | 事務所により違いあり | 扱う商品に偏る |
| 住宅購入の知識 | 専門 | 住宅専門ではない | 扱う商品に偏った知識 |
| 不動産物件の紹介 | 不動産免許取得者のため、 土地・戸建て・マンションの物件比較・アドバイスなどが可能 |
不可 | 不可 |
| 資産運用の提案 | 金融商品仲介業として 住宅ローン返済を含む資産運用提案が可能 |
不可 | 不可 |
| 相談料 | 無料 | 無料 or 有料 | 無料 |