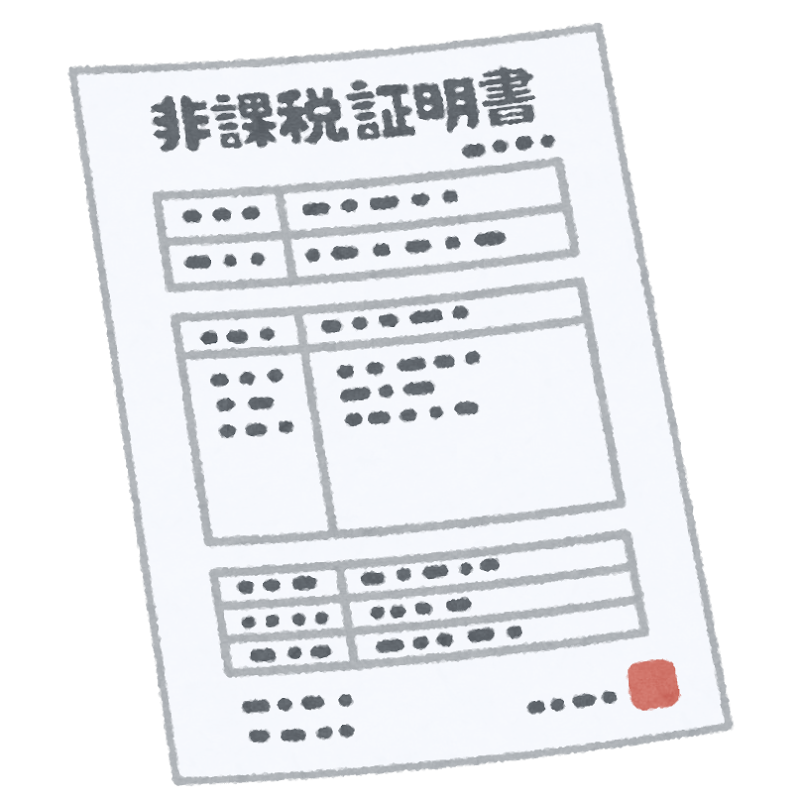ファイナンシャルプランナー(FP)コラム

住宅購入資金の贈与でかかる税金と非課税制度【2025年最新版】
執筆者
住宅購入診断士
住宅FPエキスパート
2級FP技能士
お客様の為に何ができるか『全集中』!!
ゼネラルマネージャー 松井 新吾 が執筆しました。

住宅購入のために親などから資金援助(贈与)を受ける場合、贈与税の取扱いが気になります。一般に贈与税は 「1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除)を超えると課税」 されます。しかし、親(父母・祖父母)から自分が居住する住宅の取得資金をもらった場合は、一定要件を満たせば 最大500万円~1,000万円まで非課税 になる制度があります。ここでは、住宅取得資金贈与に関する贈与税の「かかるケース・かからないケース」や、非課税制度の概要、利用条件、最新の税制動向、手続きの流れなどをわかりやすく解説します。
贈与税がかかるケース・かからないケース
- 基礎控除以内なら課税されない … 年間110万円までの贈与(たとえば両親から合わせて110万円以下)は非課税です。これは住宅資金に限らずすべての贈与に共通するルール(暦年課税の基礎控除)です。
- 住宅取得等資金の非課税特例 … 直系尊属(父母・祖父母)から、自己居住用の家屋を新築・取得・増改築するための資金をもらい、定められた要件を満たす場合、その贈与金額のうち 一般的な住宅なら500万円まで、省エネ等住宅なら1,000万円まで が贈与税の非課税枠になります。たとえば一般住宅であれば、基礎控除110万円と合わせて最大610万円までは税金がかかりません。
- 相続時精算課税制度の併用 … 住宅資金の贈与とは別枠で、60歳以上の親から子への贈与なら合計2,500万円まで非課税 の「相続時精算課税」制度もあります。要件や手続きが異なるため、より多額の援助を受ける場合は利用を検討できます。
- その他のケース … 上記以外の贈与(例えば、住宅以外の用途に資金を使う場合、贈与者が兄弟・友人の場合など)では、住宅取得特例は使えません。基礎控除110万円を超える贈与には通常どおり贈与税が課税されます。また、住宅資金贈与の非課税特例は親以外の人からの贈与では使えません。
以上のように、住宅取得資金で非課税になるのはあくまで 直系尊属からの贈与で要件を満たす場合 に限定されます。要件に当てはまらなければ、通常の贈与税(暦年課税)が適用され、税額計算上、基礎控除110万円を引いた残額に対して税率がかかります。
住宅取得資金贈与の非課税制度とは
「住宅取得等資金贈与の非課税制度」は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、受贈者本人が居住する住宅の新築・購入・増改築等の資金に充てる場合、一定額まで贈与税を免除する制度です。制度の適用期限は令和6年(2024年)~8年(2026年)まで延長されており、この期間に贈与を受けた資金が対象になります。
対象となる住宅は、自分が居住する家屋であることが前提です。また省エネ性能や耐震性能など一定以上の性能を満たす「省エネ等住宅」の場合は非課税枠が500万円上乗せされ、最大1,000万円になります。具体的には新築住宅の場合、断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上などの基準を満たす必要があります。中古住宅やリフォームの場合も省エネ等級4以上など、やや緩やかな基準が設定されています。
| 契約時期 | 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|---|
| 2022年1月1日~2026年12月31日 | 一般住宅 | 500万円(+基礎控除110万円) |
| 省エネ等住宅 | 1000万円(+基礎控除110万円) |
(表:住宅取得資金の非課税限度額)
たとえば、新築の一般住宅を購入する場合、父母から合計600万円を贈与されたとすると、基礎控除110万円と住宅資金の非課税枠500万円を合計した610万円までは贈与税がかかりません。超過分(今回の例では600万–610万=0万なので非課税)については贈与税が課税されます。
利用条件と注意点
この特例を利用するにはいくつかの条件があります。主なポイントをまとめると以下の通りです。
- 贈与者と受贈者:贈与者は父母や祖父母などの直系尊属、受贈者(贈与を受ける人)は贈与者の直系卑属(子・孫)であること。
※配偶者の親(義理の両親)は原則対象外ですが、養子縁組により直系尊属となっている場合は含まれます。 - 年齢要件:受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(高校生を除く)であること。
※以前は20歳以上でしたが、改正により18歳以上に緩和されました。 - 所得要件:贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること(家屋の床面積が40~50㎡の場合は1,000万円以下)。
- 住まい用の住宅:贈与資金は自己の居住用住宅の新築・取得・増改築に使われること。贈与を受けた翌年3月15日までに契約を締結し、資金を全額充てて建物を完成させる必要があります。その後、申告期限(翌年2/1~3/15)までに実際にその家屋に住む見込みであることも要件です。
- 過去利用の有無:受贈者が平成21年以降に同制度を受けていないこと(既に適用を受けて非課税となった金額を控除した残額が適用限度額となります)。
- 特別関係者でないこと:資金の出どころが自己の配偶者や特定の親族ではないこと。また、その親族との間で住宅の取得や工事の請負契約をしていないこと。
- 証明資料の準備:非課税を受けるには、住宅性能証明書や契約書などの書類を贈与税申告書に添付する必要があります。省エネ等住宅の場合は性能証明書の提出が求められ、建築確認の写しなど追加書類が必要なケースもあります。
これら条件を守らなかった場合、特例の適用は受けられず、通常の贈与税として扱われます。例えば、贈与の目的が住宅以外の場合、または贈与の時期・使用用途が要件に合わない場合は注意が必要です。また、贈与者・受贈者ともに確認申告が必須で、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに所轄税務署へ申告書を提出します。申告書には戸籍謄本や売買契約書の写し、贈与金の振込記録などを添付する必要があります。これを忘れると特例が受けられませんので、必ず期限内の申告を行いましょう。
2025年の税制改正動向
住宅取得資金の贈与税非課税制度は、令和6年度(2024年度)の税制改正で適用期限が令和8年(2026年)末まで延長されました。加えて、「質の高い住宅」(省エネ等性能が高い住宅)に関する要件が強化され、新築住宅はZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー等級6以上)が求められるようになっています。これにより、非課税枠500万円の上限を超えて1,000万円に届く条件は以前より厳しくなっています。
また、前回の改正で受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられ、幅広い世代で利用しやすくなりました。2025年も住宅ローン減税の見直しなどが予定されていますが、住宅取得資金の贈与税非課税措置については現時点で延長措置が決定済みであり、当面は現行ルールが継続する見込みです。今後の動向も注視しつつ、最新情報は国税庁や国土交通省の発表に注意しましょう。
贈与手続きの流れ
贈与による住宅取得資金の活用は手続きが複雑になりがちです。一般的な流れは以下のようになります。
- 計画・契約:親から資金援助を受けることを前提に、住宅の売買契約や建築契約を締結します。契約締結日を確認し、上記要件(契約から翌年3/15までに入居など)を満たすよう準備します。
- 資金の贈与:実際に親から子へ資金を贈与します。振込や領収書などで受け取りの証拠を残します。複数回に分ける場合も、すべて申告の対象になるため記録を保管してください。
- 住宅の取得・工事:贈与資金を充当して住宅を取得・建築・増改築します。領収証や請負契約書など、資金が建物取得に使われた証拠となる書類を整えましょう。
- 贈与税の申告:資金贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に、最寄りの税務署で贈与税の申告書を提出します。この申告書に「住宅取得資金の非課税特例」を適用する旨を記載し、戸籍謄本、住民票、住宅の契約書や登記事項証明書、性能証明書など必要書類を添付します。
- 税務署で確認・非課税:税務署が要件を確認し、問題なければ申告額に対する贈与税は0円(非課税)になります。不足があれば連絡が来るので、指示に従い修正申告等を行います。
以上の流れで進める際は、税制や書類準備を誤らないように注意が必要です。
まずは専門家に相談を
住宅購入資金の贈与は税制が改正されていたり、細かい要件が多いため、とても複雑です。ミスがあると税負担が増えたり、最悪の場合に特例が受けられないこともあります。まずは税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けながら計画することをおすすめします。贈与の方法や手続きについて適切にサポートを受けることで、贈与税を抑えつつ確実に住宅取得資金を活用できるでしょう。
茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】
人気コラムベスト5
-
 つくば市の10年特例用地って?
皆さんこんにちは!今回は先日茨城県つくば市のお客様がおうちを建てることが決まった「10年特例用地」についてです!つくば市には10年特例用地として住宅用地や分譲地などが存在します。続きを読む
つくば市の10年特例用地って?
皆さんこんにちは!今回は先日茨城県つくば市のお客様がおうちを建てることが決まった「10年特例用地」についてです!つくば市には10年特例用地として住宅用地や分譲地などが存在します。続きを読む
-
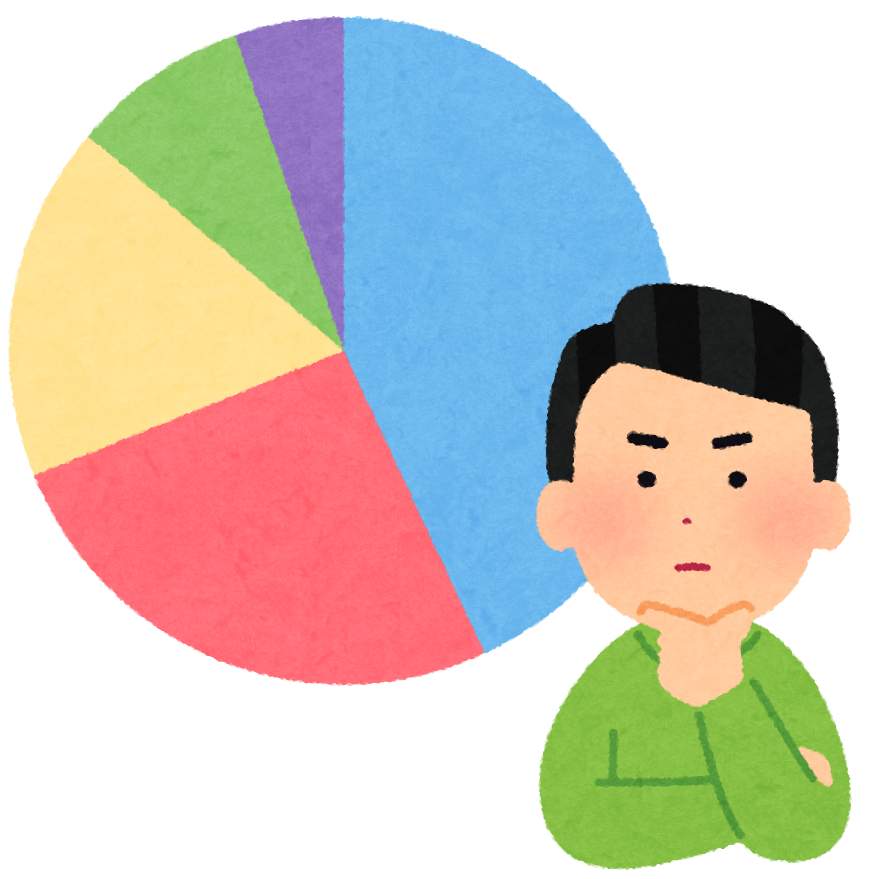 年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫?返済の安全性を考える
初めてマイホーム購入を検討している方にとって、「年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫か?」は大きな不安ですよね。結論から言えば、可能ではあるものの慎重な計画と余裕を持った返済計画が必要です。続きを読む
年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫?返済の安全性を考える
初めてマイホーム購入を検討している方にとって、「年収700万円で住宅ローン5000万円を組んでも大丈夫か?」は大きな不安ですよね。結論から言えば、可能ではあるものの慎重な計画と余裕を持った返済計画が必要です。続きを読む
-
 住宅ローンの変動金利への誤解と破綻について
住宅購入において殆どの方が住宅ローンでの借入を行いますが、ここで悩ましい問題の一つが「変動金利」と「固定金利」の選択になります。続きを読む
住宅ローンの変動金利への誤解と破綻について
住宅購入において殆どの方が住宅ローンでの借入を行いますが、ここで悩ましい問題の一つが「変動金利」と「固定金利」の選択になります。続きを読む
-
 頭金を運用するという考え方
住宅を購入するときに頭金をいくら入れようかと悩まれている方はとても多いです。また近年、積立NISAやiDeCoなどの資産運用に興味を持たれ、始めてみた方も非常に多いです。続きを読む
頭金を運用するという考え方
住宅を購入するときに頭金をいくら入れようかと悩まれている方はとても多いです。また近年、積立NISAやiDeCoなどの資産運用に興味を持たれ、始めてみた方も非常に多いです。続きを読む
-
 インフレ対策「ローン完済」か「ローン破産」かの分かれ道
日本では、1980年代のバブル崩壊以降、長期間にわたりデフレの状態が続いていました。特に日経平均株価は1989年に3万8,957円をピークに下落し、「3万円台はもう戻らない」との声も多く聞かれていました。続きを読む
インフレ対策「ローン完済」か「ローン破産」かの分かれ道
日本では、1980年代のバブル崩壊以降、長期間にわたりデフレの状態が続いていました。特に日経平均株価は1989年に3万8,957円をピークに下落し、「3万円台はもう戻らない」との声も多く聞かれていました。続きを読む
ご相談者様の声VOICE

-
最初から最後までずっと味方になってくれて、大変感謝しております!
(千葉県船橋市 S様)
-
元々、夫婦で賃貸物件に住んでいてそこまで「マイホーム」の事は近々で考えてはいませんでした。そんな中、住んでいる部屋から一部水漏れが発生!... 続きを読む

-
我が家の現在と将来をきちんと考えて下さったのが「おうちの買い方相談室」でした!
(茨城県つくば市 F様)
-
初めて「おうちの買い方相談室」に相談したのは、土地の購入を考えた時です。現在の収入で住宅ローンを組み、最後まで支払いが出来るのか?住宅ローンの審査が通るのか?不安になり、ご相談いたしました。実は、他のFPさんとも... 続きを読む
住宅購入専門のファイナンシャルプランナー(FP)による
茨城県・千葉県近郊の住宅購入・住宅ローンなどの無料相談予約 受付中です。
 下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
下記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
- 住宅購入や住宅ローンについてどこに相談して良いか分からない
- 土地・戸建て・マンションの物件比較・アドバイスもしてほしい
- 住宅ローン返済と資産運用を両立させるにはどうすればいいのか
- 住宅ローンで変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきか
- 住宅価格が高騰していて買えないのでは・・・
- 初めての住宅購入の際、まず何をすればよいのか分からない
- 住宅展示場に行くと営業マンに売り込まれそうで怖い
- お家の建築費以外にかかる費用の詳細が知りたい
- 自分の理想のお家を建ててくれる住宅会社が見つからない
当社は、住宅購入に特化した知識と経験を持つ
独立系ファイナンシャルプランナーとして、
お客様の立場に立った中立・公正なアドバイスを行っております。
| 住宅購入相談の比較 | 当社 | FP事務所 | 他の住宅相談窓口 |
|---|---|---|---|
| 所属 | 独立 | 独立 | 保険代理店など |
| 中立性 | 高い | 高い | 低い |
| 提案内容 | 幅広い | 事務所により違いあり | 扱う商品に偏る |
| 住宅購入の知識 | 専門 | 住宅専門ではない | 扱う商品に偏った知識 |
| 不動産物件の紹介 | 不動産免許取得者のため、 土地・戸建て・マンションの物件比較・アドバイスなどが可能 |
不可 | 不可 |
| 資産運用の提案 | 金融商品仲介業として 住宅ローン返済を含む資産運用提案が可能 |
不可 | 不可 |
| 相談料 | 無料 | 無料 or 有料 | 無料 |